新卒で入社したものの「仕事内容が合わない」「上司に相談しづらい」と悩み、早期退職を考える人は少なくありません。
第二新卒としてキャリアをやり直したいと感じても、「会社にどう切り出せばいいのか」「迷惑をかけない方法はあるのか」と不安がつきまといます。
そこで注目されているのが退職代行サービスです。
代行業者が会社との連絡を担ってくれるため、精神的な負担を大幅に減らせます。
しかし一方で「新卒で使っても大丈夫?」「本当に円満退社できるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、退職代行の仕組みや種類、新卒・第二新卒が利用するメリットと注意点を詳しく解説します。
さらに筆者自身がセルフ型退職代行を利用して円満退社した体験談を交え、安心して前向きなキャリアをスタートするためのヒントをお伝えします。
退職代行とは?基本の仕組みと種類

退職代行とは、依頼者に代わって勤務先へ退職の意思を伝え、退職手続きをスムーズに進めるサービスのことです。
利用者は会社に直接連絡する必要がなく、心理的な負担を大きく減らせるのが特徴です。
特に「上司に強く引き止められるのが怖い」「精神的に限界で会社に連絡できない」といった状況で活用されています。
退職代行にはいくつかの種類があり、主な分類は以下の3つです。
- 弁護士型
弁護士が運営する退職代行。
未払い残業代の請求や損害賠償への対応など、法律問題にも踏み込めるのが強み。
その分、費用は高めになる傾向があります。 - 労働組合型
労働組合が運営するサービス。
団体交渉権を持つため、会社と直接やり取りできる点が特徴。
料金は弁護士型よりも抑えられますが、法的トラブルに踏み込む対応はできません。 - セルフ型(一般事業者型)
最も利用者が多い形態で、依頼者に代わって退職の意思を会社へ伝えるシンプルなサービス。
費用は比較的安価で、スピード感がある点が魅力です。
ただし法的トラブルの交渉はできません。
どのタイプも「退職の意思を代わりに伝える」という点は共通していますが、サポート範囲や料金が異なります。
自分の状況やトラブルの有無に応じて、最適な種類を選ぶことが大切です。
新卒が退職代行を使う背景と実態

新卒として入社したものの、数か月から1年以内に「辞めたい」と考える若手社員は決して少なくありません。
厚生労働省の調査によれば、新卒3年以内の離職率は3割を超えており、早期退職は特別なことではないのです。
新卒が退職代行を利用する大きな背景には、人間関係の悩みや仕事内容とのミスマッチがあります。
学生時代に描いていた理想と現実とのギャップに苦しみ、「このまま続けても成長できないのでは」と不安を抱くケースも多いです。
さらに、精神的に疲弊してしまい、上司や人事に直接「辞めたい」と伝える気力が残っていない人もいます。
実態として、退職代行を利用する新卒は年々増加傾向にあります。
SNSや口コミでサービスの存在を知り、「自分も頼っていいのだ」と心理的ハードルが下がったことも要因のひとつです。
また、サービスが普及したことで「退職代行を使う=非常識」というイメージは徐々に薄れ、若手世代にとっては選択肢のひとつとして受け入れられつつあります。
もちろん、全ての新卒に退職代行が最適というわけではありません。
自力で円満退職できる人もいますが、「伝えられないまま体調を崩してしまう」よりは、代行サービスを利用して安全に退職する方が合理的な選択といえるでしょう。
第二新卒が退職代行を選ぶ理由

第二新卒とは、一般的に「新卒で入社してから3年以内に転職を考える若手層」を指します。
社会人経験はあるものの、まだキャリアの土台を築いている段階であり、「次のキャリアをどう選ぶか」が重要な時期です。
しかしその一方で、最初の職場を辞める際に大きなハードルを感じる人も多く、そこで退職代行を利用するケースが増えています。
第二新卒が退職代行を選ぶ主な理由は3つあります。
1つ目は、短期離職に対する不安
新卒で入社して数年以内に退職を考えると、次の就職活動で「採用担当者から『またすぐ辞めてしまうのでは?』と思われるかもしれない」という心配がつきまといます。
そのため、少しでも印象を悪くしないよう、円満に退社できる方法を選びたいと考える人が多いのです。
2つ目は、精神的な疲弊
職場環境や人間関係が原因で転職を考える場合、上司や人事との交渉が強いストレスになることもあります。
退職代行を使えば、直接やり取りする必要がなくなり、心身の負担を軽減できます。
3つ目は、キャリア再出発のスピード感
退職代行を利用すると、即日退職や短期間での退社が可能なため、次の転職活動へ早く移行できます。
若いうちにキャリアを切り替えることは、長期的にもメリットが大きいと言えるでしょう。
このように第二新卒が退職代行を利用する背景には、単なる「楽をしたい」という理由ではなく、将来を見据えた合理的な判断が含まれています。
退職代行を利用するメリット・デメリット

退職代行を利用する最大のメリットは、精神的な負担を大幅に減らせることです。
上司や人事に直接「辞めたい」と伝える必要がなく、依頼後は代行業者がすべて連絡を担ってくれます。
そのため、強い引き止めや説得を避けられ、心身を守りながら退職手続きを進められるのは大きな安心材料です。
また、即日退職が可能になるケースが多いのも利点です。
法律的には2週間前の通知が原則ですが、代行業者を通すことで会社との交渉がスムーズになり、実際には数日で退職できる例も少なくありません。
さらに、有給休暇の消化や離職票の発行など、退職後に必要な手続きについてもサポートしてくれる業者があり、次のキャリア準備に集中できます。
一方で、デメリットも存在します。
まず費用がかかる点です。
セルフ型なら1〜3万円程度、労働組合型や弁護士型になると5万円以上かかる場合もあります。
また、退職代行はあくまで「退職の意思を伝える」ことが中心であり、未払い残業代や損害賠償などの法的トラブルまで解決できるわけではありません(弁護士型を除く)。
退職代行を利用すると、会社には「本人から直接ではなく、代行業者を通じて退職の意思が伝えられた」という事実が残ります。
そのため、「上司からどう思われるだろう」「直接言わなかったことをネガティブに受け取られるのでは」と不安を抱く人も少なくありません。
「退職代行を使ったこと自体は会社に知られる」ため、人によっては「直接伝えなかった」と見られる不安を抱くこともあるでしょう。
ただし、実際には法律上問題はなく、転職活動に大きく不利になるケースは多くありません。
このように退職代行にはメリット・デメリットがあり、自分の状況に合わせて使うべきか判断することが重要です。

退職代行の法的な位置づけとリスク

退職代行サービスはここ数年で広く知られるようになりましたが、「そもそも法律的に問題はないのか?」と不安に思う人は少なくありません。
結論から言うと、退職代行そのものは違法ではありません。
労働者には憲法や労働基準法で「退職の自由」が認められており、第三者を通じてその意思を伝えることも可能だからです。
ただし、すべての退職代行が同じレベルで合法的に運営されているわけではなく、特に注意すべきなのは、業者が本人に代わって会社と交渉をしてしまうケースです。
法律上、交渉を行えるのは「弁護士」か「労働組合」に限られています。
セルフ型の事業者が無資格で交渉まで踏み込むと「非弁行為」となり、違法の恐れがあります。
利用者としては、業者がどの範囲まで対応可能かをしっかり確認することが重要です。
リスクとして考えられるのは、サービス選びを誤った場合のトラブル。
例えば「費用を支払ったのに連絡がつかない」「退職手続きが不完全で離職票が届かない」といった事例も報告されています。
また、まれに会社側から「退職代行を使うとは非常識だ」と非難されるケースもありますが、法的に退職を妨げることはできません。
安心して利用するためには、弁護士型や労働組合型など法的に根拠を持つサービスを選ぶこと、また口コミや実績を確認して信頼できる業者を見極めることが大切です。

退職代行サービスの選び方と比較ポイント

退職代行サービスは近年急増しており、料金や対応範囲もさまざまです。
そのため「どこを選べばいいのか分からない」と迷う人も多いでしょう。
ここでは信頼できるサービスを選ぶための比較ポイントを整理します。
まず注目すべきは、運営主体の違いです。
弁護士型・労働組合型・セルフ型の3つがあり、それぞれ対応できる範囲が異なります。
法的トラブルのリスクがある場合は弁護士型が安心ですが、費用は高め。
一方、費用を抑えてスピーディに退職したい人にはセルフ型が向いています。
自分の状況に応じて選ぶことが大切です。
次に、料金体系の明確さ。
基本料金のほかに追加費用がかかるのか、有給消化や離職票の手続きサポートが含まれるのかを確認しましょう。
安さだけで選ぶと「想定外の追加費用が発生した」というケースもあるため注意が必要です。
また、サポート体制も重要。
問い合わせのしやすさ(24時間対応かどうか)、相談時のレスポンスの速さ、利用者の口コミや実績を確認すると信頼性が見えてきます。
実際に利用した人の体験談は、公式サイト以上に参考になります。
さらに、新卒や第二新卒の場合は、「円満退社を意識した対応ができるか」も見極めたいポイントです。
単に退職を代行するだけでなく、今後のキャリアを踏まえて配慮のあるサポートをしてくれる業者を選べば安心です。
退職代行は「最後の橋渡し役」となる存在です。
費用・サービス範囲・信頼性の3点を軸に比較し、自分に最も合う業者を選びましょう。

体験談:セルフ型退職代行で円満退社した実例

私が退職代行を利用したのは入社17年目。
新卒や第二新卒の頃には「退職代行」という言葉はまだ一般的ではありませんでしたが、今では退職代行サービスが広く知られるようになっていたため、利用を決めました。
私自身、人間関係が悪かったわけではなく、むしろ得意分野の仕事も任されており、会社には恩も感じていました。
しかし自分の抱えていた個人的な問題で精神的に少ししんどくなり、このまま続けるのは難しいと判断しました。
特に家庭もある立場だったため、上司から強く引き止められると「自分も納得してしまい、ズルズル働き続けてしまうのではないか」という不安が大きかったのです。
そこで利用したのがセルフ型退職代行でした。
私の場合、会社への連絡をすべて代行してもらったわけではなく、退職に向けた段取りや準備のアドバイスを受けるために活用しました。
具体的には「円満退職するための手続きの流れ」「上司へ伝える際の言い方」「必要な書類や返却物の整理」などを事前に相談し、情報収集できたことが非常に役立ちました。
実際の手続きや上司への退職の意思表示は自分で行いましたが、事前準備ができていたおかげで話し合いは落ち着いて進み、引き止めも過度にならず、トラブルなく円満退職できました。
利用して感じたのは、退職代行は「逃げるための手段」ではなく、「不安を減らし、準備を整えるための心強いサポート」であり、迷いを減らし誠実に退くための相談窓口にもなり得るということ。
長年勤めた人間にとっても、有効な選択肢であると実感しました。
退職代行を使うべきか判断するチェックリスト
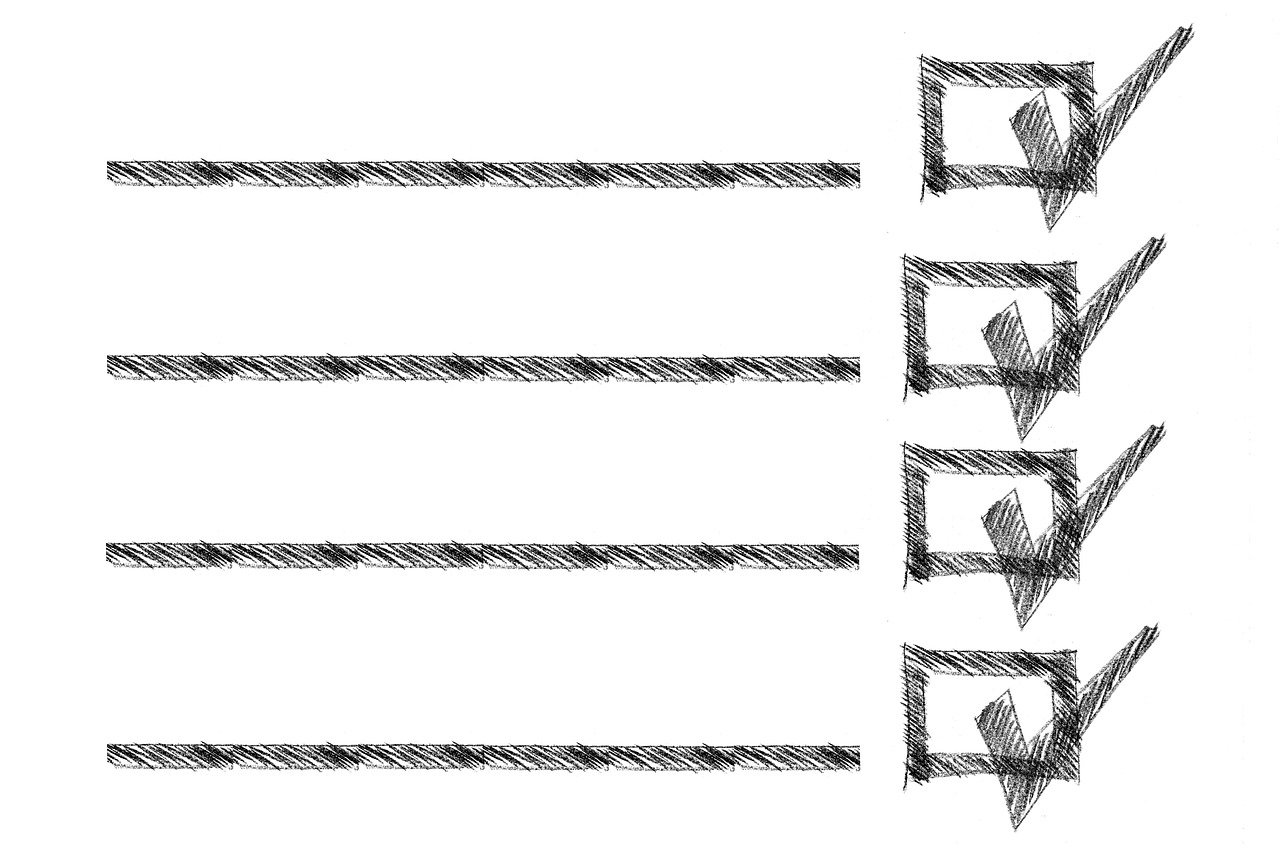
退職代行は便利なサービスですが、誰にとっても必ず必要というわけではありません。
「自分は利用すべきかどうか」を判断するために、以下のチェックリストを参考にしてみてください。
✅ 退職代行を検討した方がよいケース
- 上司や人事に退職の意思を伝えるのが強いストレスになっている
- 退職を切り出しても、引き止められる不安が大きい
- 精神的に疲弊していて、交渉を続ける余力がない
- 有給休暇の消化や退職日の調整など、スムーズに進めたい
- 家庭や健康など、時間的・精神的に余裕がない
これらに複数当てはまる場合、退職代行を利用することで負担を軽減し、冷静に次のキャリアに進むことができます。
❌ 自力で解決できるケース
一方で、以下のような人は必ずしも退職代行を使う必要はありません。
- 上司や人事に率直に伝えられる関係性がある
- 引き止められても自分の意思を貫ける自信がある
- 会社の規模が小さく、手続きがシンプルに済む
- 法的トラブルや未払い賃金の心配がない
退職代行はあくまで「選択肢のひとつ」です。
無理に使う必要はありませんが、精神的・時間的な負担を減らしたい人にとっては大きな助けとなります。
最後に大切なのは、退職代行を使うかどうかは自分の健康とキャリアを守るための判断であるということです。
周囲の目を気にするより、自分にとって最善の方法を選ぶことが、次のステップを前向きに進める第一歩になります。

FAQ|よくある質問

Q1. 新卒が退職代行を使うと転職に不利になりますか?
A. 一般的に「退職代行を使った」という事実が転職活動で直接不利になることはありません。採用担当者が重視するのは「なぜ辞めたのか」「次にどう成長したいのか」という理由です。退職理由を前向きに整理し、自分のキャリアビジョンを明確に語れるよう準備しておけば、むしろ信頼感を与えることができます。
Q2. 第二新卒でも退職代行は使えますか?
A. はい、もちろん利用可能です。第二新卒は短期離職に不安を抱く人が多いですが、退職代行を活用することで引き止めや交渉の負担を避け、スムーズに転職活動へ移行できます。重要なのは、退職後にキャリアをどう築きたいかを整理しておくことです。
Q3. セルフ型と労働組合型の違いは?
A. セルフ型は「退職の意思を伝える」ことに特化したシンプルなサービスで、費用は安くスピーディです。一方、労働組合型は団体交渉権を持つため、有給休暇の消化など会社との調整を直接行えます。ただし、法的トラブルに踏み込めるのは弁護士型のみです。
Q4. 退職代行を使えば本当に即日退職できますか?
A. 法律上は退職の申し出から2週間で効力が発生します。ただし実際には、代行業者を通じて会社が受理すれば、即日で出社を免除されるケースも多いです。「退職日自体が即日」とは限りませんが、「その日から会社に行かなくてもよくなる」ケースは珍しくありません。
Q5. 退職代行を使うと会社に悪い印象を与えますか?
A. 代行を使ったことは会社に知られますが、それが法的に問題視されることはありません。確かに「直接伝えなかった」と思われる可能性はありますが、退職届の提出や引き継ぎを誠実に行えば、円満退職は十分可能です。印象を和らげるためには礼儀を守る姿勢が大切です。
Q6. 費用はどのくらいかかりますか?
A. セルフ型は1〜3万円程度、労働組合型は2〜5万円、弁護士型は5〜10万円が相場です。費用だけでなく「どこまで対応してくれるか」も重要な比較ポイントです。追加料金の有無やサポート範囲を事前に確認しましょう。
Q7. 退職代行を使った後にトラブルが起きたらどうすればいいですか?
A. まずは利用した業者に相談し、対応可能か確認します。未払い残業代や損害賠償など法律問題に発展した場合は、必ず弁護士に相談する必要があります。安心のために、最初から法的な対応力を持つ業者を選ぶのも有効です。
まとめ
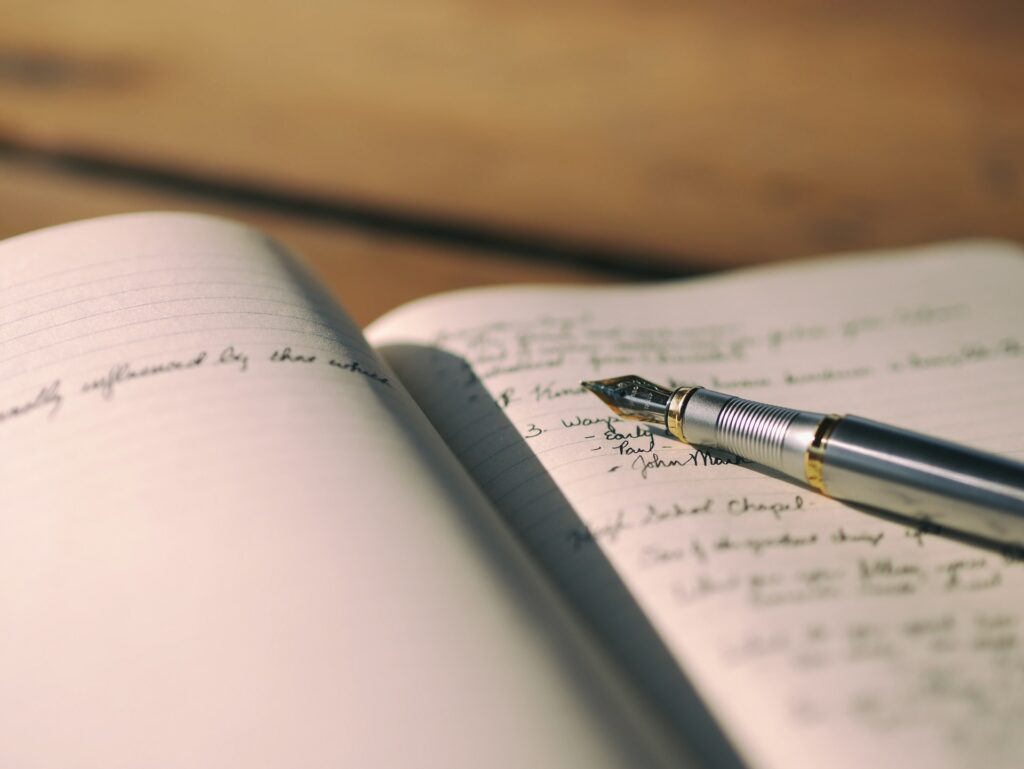
退職代行は、退職の意思を伝えることが難しい人にとって有効なサポート手段です。
新卒や第二新卒といった若手だけでなく、長年勤めてきた人にとっても「安心して次のキャリアに進むための橋渡し役」となり得ます。
この記事では、退職代行の仕組みや種類(弁護士型・労働組合型・セルフ型)、新卒や第二新卒が利用する背景、メリット・デメリット、法的な位置づけを解説しました。
また、筆者自身の体験談として、入社17年目にセルフ型退職代行を活用し、段取りや準備のアドバイスを得ながら円満退社できた事例も紹介しました。
これにより、退職代行は「逃げるための手段」ではなく、状況に応じて上手に利用できるサービスだとお伝えできたと思います。
退職は大きな決断であり、不安や迷いは誰にでもあります。
しかし、退職代行という選択肢を持っているだけで心理的な余裕が生まれ、「無理をしなくてもいい」と気づくきっかけになります。
新卒・第二新卒の方はもちろん、中堅やベテランの方も、自分の健康や家庭、将来のキャリアを守るために最適な方法を選ぶことが大切です。
退職代行はその一助として、多くの人にとって心強い存在になり得るでしょう。
👇おすすめの記事ですので参考にこちらも読んでください。


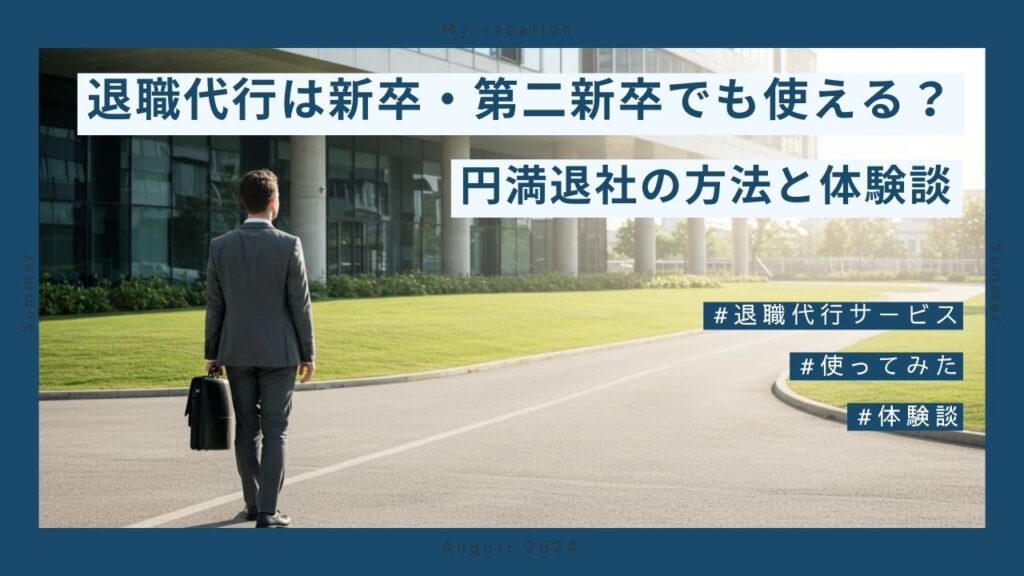



コメント