
退職を考えたとき、まず気になるのが
「退職金って実際いくらもらえるのか?」
ということではないでしょうか。
この記事では、筆者が警察官として17年間勤務し自己都合退職したリアルな体験を交えつつ、退職金の基本から税金・支給条件・注意点までをわかりやすく解説します。
退職金とは?もらえる人・もらえない人の違い
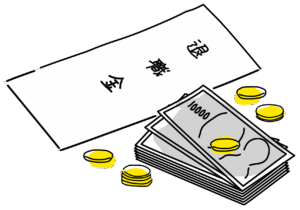
退職金とは、勤続年数や役職、退職理由などに応じて支給される一時金です。老後資金や転職期間中の生活費としての役割もあります。
もらえるケース
- 勤続年数が一定以上
- 退職金制度が会社にある
- 就業規則に明記されている
もらえない可能性のあるケース
- 勤続年数が短すぎる(例:1年未満)
- 懲戒解雇などの重大な理由での退職
- 退職金制度自体がない企業
退職金の計算方法|基本の仕組みを解説
企業によって差はあるものの、一般的な計算式は以下の通りです。
退職金の計算式(例)
退職金 = 基本給 × 支給係数 × 勤続年数 × 支給率
▶ 影響する要素:
- 勤続年数が長いほど有利
- 役職が高いほど支給係数が上がる
- 自己都合よりも会社都合・定年退職の方が支給率が高い
退職金にかかる税金のしくみ|退職所得控除とは

退職金は非課税ではありませんが、「退職所得控除」により税負担が軽減されます。
-
勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
-
勤続20年超:800万円+70万円×(年数−20年)
課税対象額 = (退職金 − 控除)× 1/2
この金額に所得税・住民税がかかります。
【体験談】警察官17年勤務・自己都合退職のリアルな退職金
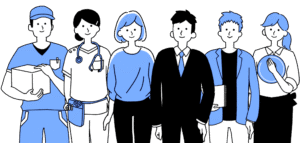
筆者は、地方勤務の警察官として17年間勤務し、巡査長のまま自己都合で退職しました。
▶ 支給された退職金:約500万円
-
昇任がなかったこと
-
定年前の自己都合退職だったこと
が金額に大きく影響しました。
退職に至った背景|家族と仕事、現場のリアル
退職理由には、家族の事情と勤務環境の問題が重なっていました。
主な背景
-
通訳スキルによる頻繁な休日呼び出し(手当なし・交通費自腹)
-
妻の妊娠中に三交替勤務へ異動 → 妻の体調悪化と死産
-
遠方への再異動(通勤片道2時間)
-
障害のある長女のため、関東への転居を決意(小学校進学のタイミング)
このように、退職金の金額以上に「辞めざるを得ない」事情があったことが、私の決断を支えました。

定年退職した警察官との比較で見える『退職金格差』
| 項目 | 定年退職 | 筆者(中途退職) |
|---|---|---|
| 勤続年数 | 約38年 | 17年 |
| 階級 | 警部補〜警部 | 巡査長 |
| 理由 | 定年 | 自己都合 |
| 退職金 | 約2,000万〜2,500万円 | 約500万円 |
差額:およそ4〜5倍の違い
長く働くこと・昇任すること・定年まで勤めることによって、退職金の金額は大きく伸びます。退職のタイミングによって生涯収入が大きく変わるため、将来設計の中で退職金の位置づけをしっかり考えることが重要です。
退職金を受け取るときの注意点
圧縮-300x225.png)
退職金を受け取る際には、次のような点に注意しましょう。
-
税金の申告:基本は源泉徴収されるが、副業等があれば確定申告も必要
-
資金計画:転職活動・引越し費用で消えることもある
-
共済年金や企業年金:手続きに時間がかかる場合あり。早めの確認を!
まとめ|退職金の金額以上に「納得できる選択」を
退職金の金額は制度や勤続年数で大きく左右されますが、その人の背景や人生の事情を無視しては語れないお金でもあります。
自分の価値観と向き合い、制度を正しく理解した上で「後悔のない退職」を選ぶことが、何より大切です。









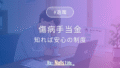
コメント