- 辞めたい
- 思ってたのと違った
- 退職届ってどうやって書くの?
- いつ出すの?

「辞めたいと思ってしまうのは甘え?」
そんなふうに悩んでいませんか?
新卒で入社したばかりでも、仕事や人間関係に違和感を覚え、「このままでいいのか」と不安になる方は少なくありません。
この記事では、退職を検討しているあなたに向けて、以下の内容をやさしく解説します:
-
退職願と退職届の違い
-
提出までの流れとタイミング
-
書き方のルールとテンプレート
-
円満に退職するためのポイント
自分の気持ちに正直になり、前向きな一歩を踏み出すために、ぜひ参考にしてください。
退職届の基礎知識と役割
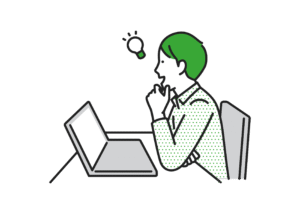
退職届とは何か
退職届は、会社に「いつをもって退職します」と正式に伝えるための書面です。
口頭での申し出では、あとで言った言わないの揉め事になりやすいのに対し、退職届はきちんとした記録になります。
提出をきっかけに、社内では引き継ぎの手配や各種手続きが動き出します。
だからこそ、内容は余計な飾りをつけず、見やすい形にまとめることが大切です。
退職届が必要となるケース
正社員として勤めている人が自己都合で退職する場合、多くの会社では退職届の提出を求めます。
上司に合意を得たあと、指定の様式や提出先に沿って出すのが通常の流れです。
会社側の都合で契約が終了する場合など、こちらから出さないこともありますが、迷ったら就業規則を確認し、必要であれば早めに用意しておくと安心です。
提出前の段階から、退職届のフォーマットを軽く確認しておくと、その後の段取りもスムーズになります。
退職願との違い
似ている言葉に「退職願」があります。
退職願は「辞めたいので許可してほしい」と会社にお願いする文書で、会社の了承前の段階で出すものです。
一方、退職届は「辞めることを決めたので通知します」という最終の通告で、提出後の取り消しは難しくなります。
退職願と退職届の違いを理解するコツは、「願」は相談の基礎、「届」は決定の知らせ、と覚えておくことです。
状況に合わせて適切なほうを選ぶことで、その後のやり取りが円滑になります。
退職届の書き方・提出タイミング・マナー
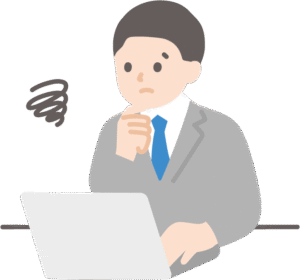
正しい退職届の書き方
基本フォーマットと必須項目
退職届の書き方は、とてもシンプルです。
上から順番に「タイトル」「前文」「本文」「日付」「所属と氏名」の順で記載します。
タイトルには大きく「退職届」と書き、その下に「私儀」または「私事」と入れます。
本文は「一身上の都合により〇年〇月〇日をもって退職いたします」と必要最小限にまとめます。
最後に提出日と自分の所属部署名、氏名を書き、捺印します。
退職届のフォーマットは会社で指定されている場合もあるため、必ず確認しましょう。
指定がない場合は、白無地の便箋を使い、ていねいに手書きするか、きれいに印刷したものを用意します。
退職理由の書き方
退職理由の書き方は、とても重要です。
円満退職を目指す場合は「一身上の都合により」と書くのがもっとも安全です。
細かい事情は文書に記載せず、口頭で必要な範囲だけを伝えます。
会社都合退職の場合は「会社都合により退職いたします」としますが、この場合も就業規則や上司の指示に従うことが大切です。
感情的な言葉や不満は書かないのが基本です。

提出タイミングの目安と法律上の基準
退職届 提出タイミングは、法律上は退職日の2週間前までに提出すれば問題ありません。
ただし、これはあくまで最終ラインで、実際にはもっと早めに行動することが望ましいでしょう。
多くの会社では、就業規則で1か月前までの提出を定めています。
円満退職のためのポイントとして、引き継ぎの時間を十分に確保できるよう、退職希望日の2〜3か月前には上司に相談し、その後で正式に退職届を提出すると安心です。
封筒の書き方と提出方法
封筒は白無地で郵便番号枠のないものを選び、表面には「退職届」と記載し、裏面に所属部署と氏名を書きます。
手渡しする場合は封はしませんが、郵送する場合は封をして、簡易書留など記録が残る方法で送ります。
退職届の提出方法は、基本的に直属の上司へ手渡しします。
人事部や総務部が提出先であっても、まずは上司に報告することがマナーです。
提出の場では、簡潔に退職の意思と感謝の気持ちを伝えると良い印象が残ります。
円満退職を叶えるためのポイントと注意点

円満退職のための事前準備
円満退職のためのポイントは、まず心の準備から始めます。
自分がなぜ退職したいのかを整理し、落ち着いて事実を伝えられるようにしておきましょう。
次に、就業規則を確認し、退職届 提出タイミングや引き継ぎ期間を把握します。
これをもとに退職日を逆算し、計画的に動くことが大切です。
また、上司への報告はアポイントを取り、落ち着いた場所で行います。
退職理由の書き方にも配慮し、前向きな表現を選ぶことで相手の受け取り方がやわらかくなります。

提出時・提出後に気をつけること
退職届の提出方法は手渡しが基本ですが、その場での言葉選びにも注意が必要です。
提出時には、これまでの感謝を一言添えると、円満な雰囲気が生まれます。
提出後は引き継ぎ業務に集中し、後任が困らないよう資料やマニュアルを整えます。
退職届提出後の流れとしては、退職日までに引き継ぎを完了させ、私物の整理、貸与品の返却、離職票や源泉徴収票など必要書類の受け取りが一般的です。
最後の日には同僚やお世話になった人へ直接あいさつをして締めくくります。
トラブルを避けるための対応
退職届の注意点として、感情的にならないことがあげられます。
不満や批判を前面に出すと、人間関係がこじれたり、今後のキャリアに影響する可能性があります。
また、繁忙期や重要なプロジェクト中の退職は、周囲への負担が大きくなるため避けたほうが無難です。
やむを得ない場合は、早めに相談し、対応策を共有しましょう。
退職願と退職届の違いを理解し、状況に応じて使い分けることもトラブル回避につながります。
退職届サンプル・テンプレートとまとめ
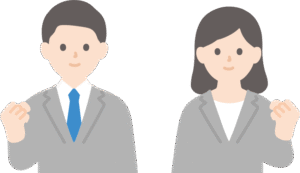
退職届サンプル例文
退職届の書き方 サンプルは、初めての人でもそのまま使える形にしておくと安心です。
以下は自己都合退職の一般的な例です。
退職届
私儀
このたび一身上の都合により、〇年〇月〇日をもちまして退職いたします。
令和〇年〇月〇日
〇〇株式会社
〇〇部 〇〇課
氏名(印)
このように、余計な情報は入れず、日付や氏名など必要な部分だけを正しく記入します。
会社によっては専用のフォーマットがある場合もあるため、必ず確認してから書きましょう。
利用できるテンプレート
最近は、インターネット上で無料ダウンロードできる退職届のフォーマットやテンプレートが多数あります。
WordやPDF形式のものを印刷して手書きにしたり、そのまま印字して使うことも可能です。
ただし、会社独自で用紙サイズや書式の指定がある場合は、それに従うことが大切です。
テンプレートを利用する際は、会社のルールと照らし合わせてから使用しましょう。
まとめ:安心して次のステップへ進むために
退職届は、ただ書いて出すだけではなく、提出タイミングや書き方、マナーを守ることで円満退職につながります。
退職理由の書き方や封筒の扱い、提出方法まで丁寧に整えることで、相手に誠意が伝わります。
また、退職届 提出後の流れを理解しておけば、引き継ぎや事務手続きもスムーズです。
この一連の流れをしっかり踏めば、退職は新しいスタートへの前向きな一歩になります。
準備を整え、自信を持って次の環境へ進みましょう。








コメント